総合司会は日本農学アカデミー 渡部終五理事。開会挨拶は日本農学アカデミー生源寺眞一会長。基調講演は「食料・農業・農村基本計画の概要」女子栄養大学中嶋康博教授。そこから講演が「経営・ビジネス視点でみる農業の課題と可能性」八ヶ岳農業大学校・丸山侑佑校長。「農企業にみる戦略的経営と共通価値の創造」東京農業大学・渋谷往男教授。「スマート農業の役割」北海度大学大学院農学研究院長・野口 伸教授。「肥料の安定供給リスクと食料安全保障」農林中金総合研究所・小針美和主席研究員。そして小生の「農業・食・エネルギーをめぐる現場の新たな潮流」と続く。
開催趣旨には「本年4月に食料・農業・農村基本法改正後初の「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定された。わが国の農業、農村は「国の基」とされるが、その持続性を脅かす国内外のさまざまな問題が指摘されており、基本計画ではそれらへの対処方針が示されている。本シンポジウムでは基本計画の枠組みやポイントを紹介しながら、わが国の農業が直面する現状と将来の目指すべき姿をさまざまな観点から議論する」とある。
●食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日 閣議決定)

公開講演の講師メンバーの一員になったのは、小田原市の老舗「鈴廣蒲鉾」の鈴木博晶会長が日本農学アカデミー渡部終五理事に推薦してくださったことからだった。渡部終五理事は、水産物研究の専門家。「鈴廣蒲鉾」の「魚肉たんぱく研究所」に携わっていらっしゃる。
どうやら鈴木博晶会長が「エネルギーから経済を考えるネットワーク」(略称=エネ経)のメールマガジン「【連載】金丸弘美氏に聞く 農業・食・エネルギーの現場から」を読んでくださっていらっしゃったようなのだ。
●【連載】金丸弘美氏に聞く 農業・食・エネルギーの現場から
素晴らしい発表の場をいただいた。メルマガで紹介してきたように、現場からの新たな動きを伝えたいと思っている。まだ案内がされたばかりだが、すでに全国から参加や反響のメールが続々と届いている。
「食料・農業・農村基本計画の概要」を読むと、自給率は38%と1965年から下がり続けたまま。コメの需要と生産も下がっている。肥料の多くは輸入だ。農産物の輸入も増えている。基幹的農業従事者数は約20年間で半減、2000年の240万人から2024年は111万4千人にまで減少。65歳以上は79万9千人と全体の71.7%、平均年齢は69・2歳となっている。など課題は多い。担い手の支援や、遊休地の活用など、さまざまな政策が出されている。しかし現場では、手をこまねいているわけではない。若い世代から新なイノベーションが次々と生まれている。
どうやら鈴木博晶会長が「エネルギーから経済を考えるネットワーク」(略称=エネ経)のメールマガジン「【連載】金丸弘美氏に聞く 農業・食・エネルギーの現場から」を読んでくださっていらっしゃったようなのだ。
●【連載】金丸弘美氏に聞く 農業・食・エネルギーの現場から
素晴らしい発表の場をいただいた。メルマガで紹介してきたように、現場からの新たな動きを伝えたいと思っている。まだ案内がされたばかりだが、すでに全国から参加や反響のメールが続々と届いている。
「食料・農業・農村基本計画の概要」を読むと、自給率は38%と1965年から下がり続けたまま。コメの需要と生産も下がっている。肥料の多くは輸入だ。農産物の輸入も増えている。基幹的農業従事者数は約20年間で半減、2000年の240万人から2024年は111万4千人にまで減少。65歳以上は79万9千人と全体の71.7%、平均年齢は69・2歳となっている。など課題は多い。担い手の支援や、遊休地の活用など、さまざまな政策が出されている。しかし現場では、手をこまねいているわけではない。若い世代から新なイノベーションが次々と生まれている。

石坂産業がごみの不法投棄がされていた里山を地域と連携し再生。環境を学び有機の農業の実践の場とした「三富今昔村」

今回の公開講演では、これらの現場からの新たなイノベーションを伝える予定だ。
「鈴廣蒲鉾」とのおつきあいは長く、これまで現地取材をさせていただいている。実は、国の農業政策のなかには、地域資源を活かして、さまざまな食・環境・地域らしさ、地域事業社、人を繋ぎ連携することで、農業から観光に繋ぎ、持続社会を創ることが謳われている。そのことは、今年度、出された「地方創生2・0」でも明記されている。
●地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)
「鈴廣蒲鉾」は、江戸期に生まれた老舗。昔ながらの蒲鉾づくりから大胆な変革を行い、体験工房、レストラン、地ビール工房、カフェ、直売所などを連携し、消費者のニーズにあった観光にも連携する新たな展開を行っている。まさに、今、もとめられている地域の在り方を形にしている先進事例を開拓してきたところだ。
東日本大震災のあと、「鈴廣蒲鉾」副社長であった鈴木悌介さん(現相談役)を中心に「エネルギーから経済を考えるネットワーク」(略称=エネ経)が誕生した。
これは、中小企業を中心に、再生可能エネルギー、脱炭素を現場から進めていこうという取り組み。原発反対だけでは先へ進まない。この考えは、ドイツ・フライブルグの運動と合致する。実は、東日本大震災の前にドイツ・フライブルグの環境の都市づくりの現地調査ツアーを企画し行った。フライブルグでは、かつて原発を推進する予定だった。しかしチェルノブイリ原発事故の影響があり、原発計画を撤廃。まずは、足元からできることを進めることとなる。会社や家屋の太陽光設置、住宅の脱炭素、住宅政策の大幅な改善、小水力発電、地下水との置換による冷暖房の電気削減、公共交通の優先、住宅周辺の緑のカーテン、自転車道の整備、街中の歩行者優先、オーガニックの農業推進、山林の管理など、あらゆる取り組みがおこなわれている。その身近なことから、できることはすべて行うという考えと実践に感銘した。
フライブルグは、世界から環境視察が訪れている。そのために、役場には、解説を行う会場も設けてあり、専任の担当者もいる。案内は有料だ。実は、環境の取り組みを徹底して行っているうちに、世界各地から視察が訪れるようになり、とても手が回らない。そこから有料視察として、町を案内し、現場をみせていくという活動が生まれる。近郊の農村は古い家屋をリノベーションして、それが宿や食事処になるという農村観光の取り組みにも繋がっている。しかも景観も配慮されている。徹底的な環境政策が、結果的には経済をもたらしている。現地レポートは書籍でも取り上げた。
●『地域ブランドを引き出す力 トータルマネジメントが田舎を変える!』(合同出版)
「鈴廣蒲鉾」とのおつきあいは長く、これまで現地取材をさせていただいている。実は、国の農業政策のなかには、地域資源を活かして、さまざまな食・環境・地域らしさ、地域事業社、人を繋ぎ連携することで、農業から観光に繋ぎ、持続社会を創ることが謳われている。そのことは、今年度、出された「地方創生2・0」でも明記されている。
●地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)
「鈴廣蒲鉾」は、江戸期に生まれた老舗。昔ながらの蒲鉾づくりから大胆な変革を行い、体験工房、レストラン、地ビール工房、カフェ、直売所などを連携し、消費者のニーズにあった観光にも連携する新たな展開を行っている。まさに、今、もとめられている地域の在り方を形にしている先進事例を開拓してきたところだ。
東日本大震災のあと、「鈴廣蒲鉾」副社長であった鈴木悌介さん(現相談役)を中心に「エネルギーから経済を考えるネットワーク」(略称=エネ経)が誕生した。
これは、中小企業を中心に、再生可能エネルギー、脱炭素を現場から進めていこうという取り組み。原発反対だけでは先へ進まない。この考えは、ドイツ・フライブルグの運動と合致する。実は、東日本大震災の前にドイツ・フライブルグの環境の都市づくりの現地調査ツアーを企画し行った。フライブルグでは、かつて原発を推進する予定だった。しかしチェルノブイリ原発事故の影響があり、原発計画を撤廃。まずは、足元からできることを進めることとなる。会社や家屋の太陽光設置、住宅の脱炭素、住宅政策の大幅な改善、小水力発電、地下水との置換による冷暖房の電気削減、公共交通の優先、住宅周辺の緑のカーテン、自転車道の整備、街中の歩行者優先、オーガニックの農業推進、山林の管理など、あらゆる取り組みがおこなわれている。その身近なことから、できることはすべて行うという考えと実践に感銘した。
フライブルグは、世界から環境視察が訪れている。そのために、役場には、解説を行う会場も設けてあり、専任の担当者もいる。案内は有料だ。実は、環境の取り組みを徹底して行っているうちに、世界各地から視察が訪れるようになり、とても手が回らない。そこから有料視察として、町を案内し、現場をみせていくという活動が生まれる。近郊の農村は古い家屋をリノベーションして、それが宿や食事処になるという農村観光の取り組みにも繋がっている。しかも景観も配慮されている。徹底的な環境政策が、結果的には経済をもたらしている。現地レポートは書籍でも取り上げた。
●『地域ブランドを引き出す力 トータルマネジメントが田舎を変える!』(合同出版)

フライブルグの緑化された電車道。歩けるまちづくり

エネ経では、交流・シンポジウム、現地調査レポート配信が行われている。なかでもエネ経の取り組みで知った、再生可能エネルギーを地域から生み出す取り組みをしてきた兵庫県「宝塚すみれ発電」の井上保子さん、「一般社団法人 徳島地域エネルギー」の豊岡和美さん、長野県「NPO法人上田市民エネルギー」藤川まゆみさん、など、実践で現場から形にしてきた人たちの活動には目を見張った。足元から産官学を連携され、ノウハウ連携事業、脱炭素化の実践を推進している。「宝塚すみれ発電」の井上保子さん、NPO法人上田市民エネルギー」藤川まゆみさんは、現地取材を。「一般社団法人 徳島地域エネルギー」の豊岡和美さんは、日本ペンクラブ環境委員会のセミナー講師として推薦し、その具体的な活動もレポートさせていただいた。取り組みをしているのは女性たち。生活者の視点で足元から形にし見える化をされている。
●宝塚すみれ発電
●一般社団法人 徳島地域エネルギー
●NPO法人上田市民エネルギー
彼女たちの活動と地域農業振興政策が巧くかみ合うといいなと願っている。
●宝塚すみれ発電レポート
「再生可能エネルギーの発電所で持続的な農業を目指す」
「株式会社宝塚すみれ発電」代表取締役井上保子さん
■(パート1)
■(パート2)
●宝塚すみれ発電
●一般社団法人 徳島地域エネルギー
●NPO法人上田市民エネルギー
彼女たちの活動と地域農業振興政策が巧くかみ合うといいなと願っている。
●宝塚すみれ発電レポート
「再生可能エネルギーの発電所で持続的な農業を目指す」
「株式会社宝塚すみれ発電」代表取締役井上保子さん
■(パート1)
■(パート2)

宝塚すみれ発電・井上保子さん
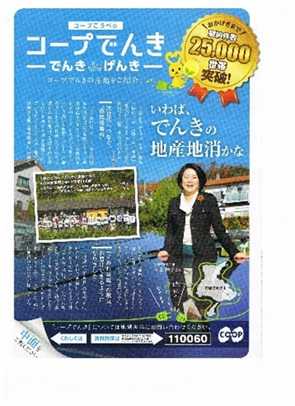

上田市民エネルギー・藤川まゆみさん
