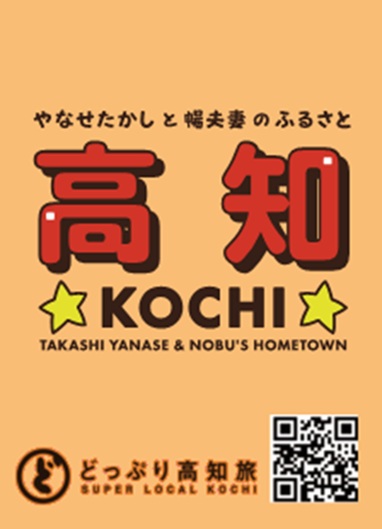
■「高知県内の無料入場観光施設」のご案内 【有効期限:令和9年3月31日】
実は、名刺の裏が「高知県観光施設等無料入場券」になっていて、高知城、高知県立美術館、高知県立坂本龍馬館、高知県立牧野植物園、高知県立足摺海洋館など23か所の文化施設が5名まですべて無料で入れる。香美市やなせたかし記念館も無料で入れる。
そのことで、名刺を差し上げた方から、とても喜ばれるのだ。
実は、名刺の裏が「高知県観光施設等無料入場券」になっていて、高知城、高知県立美術館、高知県立坂本龍馬館、高知県立牧野植物園、高知県立足摺海洋館など23か所の文化施設が5名まですべて無料で入れる。香美市やなせたかし記念館も無料で入れる。
そのことで、名刺を差し上げた方から、とても喜ばれるのだ。

名刺表にQRコードがあり、そこから高知県の見どころ ガイド『どっぷり高知旅』へ飛べる。
■どっぷり高知旅
「やなせたかしゆかりの地高知スタンプラリー」「高知グルメガイド」、「女子旅でさがす」「家族旅行で探す」「絶景で探す」「季節でさがす」「温泉めぐりの旅」を始めさまざまコースが連動している。
「やなせたかしワールド・どっぷり旅に出かけよう!」もある。
■やなせたかしワールド・どっぷり旅に出かけよう!
■どっぷり高知旅
「やなせたかしゆかりの地高知スタンプラリー」「高知グルメガイド」、「女子旅でさがす」「家族旅行で探す」「絶景で探す」「季節でさがす」「温泉めぐりの旅」を始めさまざまコースが連動している。
「やなせたかしワールド・どっぷり旅に出かけよう!」もある。
■やなせたかしワールド・どっぷり旅に出かけよう!

高知県の食のガイドや割引の特典キャンペーン一覧も飛び出してくる。
NHKの朝ドラ(2025年春の連続テレビ小説「あんぱん」)に連動しているのは、もちろんだが、旅先のさまざまなコースがしっかり練られており、どんな旅を楽しむか案内があり体験できるようになっている。足元のコンテンツを、丁寧に拾い上げ、その見どころ、コース、食べるところ、自然体験などのガイドを練り上げ、そこから発信していくという仕組み。下地がしっかり作られている。そのマネジメントが素晴らしい。
NHKの朝ドラ(2025年春の連続テレビ小説「あんぱん」)に連動しているのは、もちろんだが、旅先のさまざまなコースがしっかり練られており、どんな旅を楽しむか案内があり体験できるようになっている。足元のコンテンツを、丁寧に拾い上げ、その見どころ、コース、食べるところ、自然体験などのガイドを練り上げ、そこから発信していくという仕組み。下地がしっかり作られている。そのマネジメントが素晴らしい。

高知県を訪れた県外観光客入込数は472万人と、これまでの最高
高知県の観光データによると2024年(令和5年)に高知県を訪れた県外観光客入込数は472万人と、これまでの最高となっている。
2024年は、NHK連続テレビ小説「らんまん」の主人公は、やはり高知出身の牧野富太郎。放送に合わせ「牧野博士の新休日~らんまんの舞台・高知~」と名刺が連動するというもの。
■高知県観光博覧会
高知県の観光データによると2024年(令和5年)に高知県を訪れた県外観光客入込数は472万人と、これまでの最高となっている。
2024年は、NHK連続テレビ小説「らんまん」の主人公は、やはり高知出身の牧野富太郎。放送に合わせ「牧野博士の新休日~らんまんの舞台・高知~」と名刺が連動するというもの。
■高知県観光博覧会
名刺は、毎年、テーマがある。
2021年は「あなたの新休日」でデザインは海でのゴムボートを漕ぐ人。自然体験がテーマ。
2022年は「高知の味曜日」で食がテーマ。
名刺のデザインをよく観ると4種類が作成されている。
高知の名物、かつお(春)、あかうし(夏)、田舎ずし(秋)、うつぼ(冬)のデザイン。嬉しそうに食を人が囲んでいる。かつおは魚の鰹。あかうしは高知県独自の褐色をした牛。田舎ずしは山間地で魚のないところで生まれた郷土食で、高知特産の柚子酢でしめ、ミョウガや椎茸、タケノコ、コンニャクなどを種にして握った彩も楽しい寿司だ。うつぼは、どう猛な細長い魚だが白身で美味だ。
高知県観光特使に任命されているのは498名/組。
毎年テーマがあり、その案内が、足元からしっかり練られることでコンテンツの充実が、積み上げられる。
2021年は「あなたの新休日」でデザインは海でのゴムボートを漕ぐ人。自然体験がテーマ。
2022年は「高知の味曜日」で食がテーマ。
名刺のデザインをよく観ると4種類が作成されている。
高知の名物、かつお(春)、あかうし(夏)、田舎ずし(秋)、うつぼ(冬)のデザイン。嬉しそうに食を人が囲んでいる。かつおは魚の鰹。あかうしは高知県独自の褐色をした牛。田舎ずしは山間地で魚のないところで生まれた郷土食で、高知特産の柚子酢でしめ、ミョウガや椎茸、タケノコ、コンニャクなどを種にして握った彩も楽しい寿司だ。うつぼは、どう猛な細長い魚だが白身で美味だ。
高知県観光特使に任命されているのは498名/組。
毎年テーマがあり、その案内が、足元からしっかり練られることでコンテンツの充実が、積み上げられる。
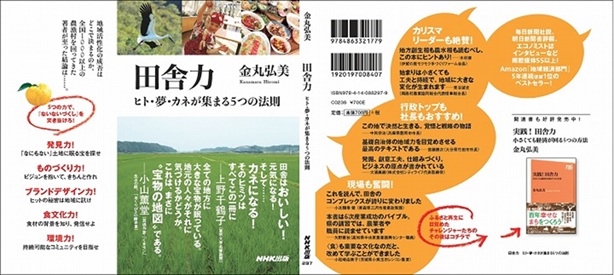
小説「県庁おもてなし課」もまちづくりに連動
よく尋ねられるのが「高知県出身でないのに、なぜ高知県観光特使なのですか」ということ。実は、私の出身は佐賀県唐津市。
私が「高知県観光特使」を拝命したのは2011年。
高知県の「ゆずポン酢」で有名な馬路村農協を始め各地の食の地域づくりを紹介した本「田舎力 ヒト・カネ・モノが集まる5つの法則」(NHK生活人新書)
この本を読んでくださった県庁の矢野喜秋さんから連絡があり高知県知事直轄事業・農業人材育成創造事業総合アドバザーになってほしいと言われ、2010年から2015年まで毎月高知県に伺うこととなった。高知県の各地を訪ね、食の地域づくりを一緒に考えていくことが始まった。
よく尋ねられるのが「高知県出身でないのに、なぜ高知県観光特使なのですか」ということ。実は、私の出身は佐賀県唐津市。
私が「高知県観光特使」を拝命したのは2011年。
高知県の「ゆずポン酢」で有名な馬路村農協を始め各地の食の地域づくりを紹介した本「田舎力 ヒト・カネ・モノが集まる5つの法則」(NHK生活人新書)
この本を読んでくださった県庁の矢野喜秋さんから連絡があり高知県知事直轄事業・農業人材育成創造事業総合アドバザーになってほしいと言われ、2010年から2015年まで毎月高知県に伺うこととなった。高知県の各地を訪ね、食の地域づくりを一緒に考えていくことが始まった。

同じころ、角川書店(現KADOKAWA)から連絡があり高知県出身の小説家・有川浩(ひろ)さんが、私の本を読んでくださり、県庁の職員との座談会が実現することになった。
県庁を舞台にした「県庁おもてなし課」の新聞小説を連載されていて本になったら座談会も収録するという話しだった。しかし小説に座談会が載るのか半信半疑だった。ところが小説が出て本屋でみたら座談会が掲載されている。
■「県庁おもてなし課」有川浩著(KADOKAWA)
県庁を舞台にした「県庁おもてなし課」の新聞小説を連載されていて本になったら座談会も収録するという話しだった。しかし小説に座談会が載るのか半信半疑だった。ところが小説が出て本屋でみたら座談会が掲載されている。
■「県庁おもてなし課」有川浩著(KADOKAWA)
このあと3・11東日本大震災が起こる。有川さんのホームページには、被災地支援で印税を寄付するとあった。私もせめて本を買ってPRでもと思い角川書店に連絡をして50冊をお願いした。送られてきた本は、すべてがサイン入り。ところが請求書がない。それで問い合わせたら「プレゼントします」とのこと。驚いた。そこで知っている限りの発信力のある方々にお贈りした。するとほとんど方々が丁寧にお手紙をくださった。なかには小説に出てくるところをすべて巡り感想をくださった方もいた。それらの手紙をコピーしてファイルにし、尾崎正直高知県知事(当時)と角川書店にお送りした。すると高知県から「観光特使になってください」と連絡がきたというわけだ。
角川書店から電話があり「ここまでしてくださったのですか」と言われ「これくらしかできませんから」と言ったら「あと50冊送ります」と、さらに50冊が届いた。それでまた発信力のある方々に贈呈をしたというわけだ。
小説を読むと「観光特使」の名刺のことも小説の重要テーマとして出てくる。ほかにない特徴ある名刺にするために無料入場券付きにすることも書いてある。
そのいきさつが傑作だ。これは、作家の有川浩さんの体験と連動している。主人公の作家が、高知県から観光特使になってほしいと依頼がある。しかし、ひとつきたっても連絡がない。いまどきネットで1日で名刺ができるのに、すぐに連絡もないとは、どういうことと。自分は作家で、そんなに名刺を配る機会がない。また観光特使名刺というのは、どこの自治体でもやっている。いっそ、名刺が地域の文化施設、すべて無料で入れる入場券にしたらどうだとあり、つまり小説と「観光特使名刺」は見事にリンクしていてドラマにもなっているのだ。しかも小説は映画にもなった。
高知県に「県庁おもてなし課(現在は、おもてなし室)」は実在する。
さらに小説のテーマが、地域のあるものすべが魅力的であり、それらを観光に活かすというもの。小説と高知県の地域発信の実践も見事リンクしている。
角川書店から電話があり「ここまでしてくださったのですか」と言われ「これくらしかできませんから」と言ったら「あと50冊送ります」と、さらに50冊が届いた。それでまた発信力のある方々に贈呈をしたというわけだ。
小説を読むと「観光特使」の名刺のことも小説の重要テーマとして出てくる。ほかにない特徴ある名刺にするために無料入場券付きにすることも書いてある。
そのいきさつが傑作だ。これは、作家の有川浩さんの体験と連動している。主人公の作家が、高知県から観光特使になってほしいと依頼がある。しかし、ひとつきたっても連絡がない。いまどきネットで1日で名刺ができるのに、すぐに連絡もないとは、どういうことと。自分は作家で、そんなに名刺を配る機会がない。また観光特使名刺というのは、どこの自治体でもやっている。いっそ、名刺が地域の文化施設、すべて無料で入れる入場券にしたらどうだとあり、つまり小説と「観光特使名刺」は見事にリンクしていてドラマにもなっているのだ。しかも小説は映画にもなった。
高知県に「県庁おもてなし課(現在は、おもてなし室)」は実在する。
さらに小説のテーマが、地域のあるものすべが魅力的であり、それらを観光に活かすというもの。小説と高知県の地域発信の実践も見事リンクしている。

国のデジタル田園都市国家構想の有料事例
現在、国は、デジタル田園構想を政策で打ち出している。
■「デジタル田園都市国家構想」(内閣府)
それぞれの地域の魅力をデジタルで発信し、「デジタルの力で、地方が日本の主役となる」とあり、「地方に仕事をつくる」「人の流れをつくる」「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「魅力的な地域をつくる」とある。これらの実現するためには、まずは足元になにができ、どんな人材育成があり、どんな魅力的なコンテンツがあるかあらいださないといけない。まずはアナログが必要だ。それを高知県は丁寧に拾い上げている。
高知県は早くから地域の人材育成事業を手掛けていて、産官学金融包括協定を結んでおり、足元から人づくり、仕事づくり、人材支援・投資を手掛けてきたところだ。
現在、国は、デジタル田園構想を政策で打ち出している。
■「デジタル田園都市国家構想」(内閣府)
それぞれの地域の魅力をデジタルで発信し、「デジタルの力で、地方が日本の主役となる」とあり、「地方に仕事をつくる」「人の流れをつくる」「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「魅力的な地域をつくる」とある。これらの実現するためには、まずは足元になにができ、どんな人材育成があり、どんな魅力的なコンテンツがあるかあらいださないといけない。まずはアナログが必要だ。それを高知県は丁寧に拾い上げている。
高知県は早くから地域の人材育成事業を手掛けていて、産官学金融包括協定を結んでおり、足元から人づくり、仕事づくり、人材支援・投資を手掛けてきたところだ。

高知県産学官民連携センター(ココプラ=ココはイノベーションを生み出すプラットフォームの略))があり、だれでもが事業スキルを高め、学び仕事に結び、融資も受けられる仕組みがある。人材育成事業がされているのである。
■高知県産学官民連携センター
「高知県産業振興計画」がしっかり作成されており、目的が明確化されている。
グラフを多用に用いオールカラーでわかりやすく絵解きされ数値目標もだされている。これによって県知事から現場職員まで課題と目標が明確となり指針がぶれることがない。
■高知県産学官民連携センター
「高知県産業振興計画」がしっかり作成されており、目的が明確化されている。
グラフを多用に用いオールカラーでわかりやすく絵解きされ数値目標もだされている。これによって県知事から現場職員まで課題と目標が明確となり指針がぶれることがない。
これらの背景には高知県は中山間地が9割を占める。山間地の人口減は、1960年から2015年の間に46.9%減少、全体で県全体の人口減少は14.8%となっていた。また若手の県外流出、生産年齢の減少、このままでは経済が縮小してしまう。そこから経済体質強化の指針がうち出された。
また、県が行った世論調査で、人材育成と人材の確保が求められたことから、本格的な人材育成事業が始まる。その実践を足元から打ち出している。
これからの「地方創生」の、モデルともいえるものだ。
また、県が行った世論調査で、人材育成と人材の確保が求められたことから、本格的な人材育成事業が始まる。その実践を足元から打ち出している。
これからの「地方創生」の、モデルともいえるものだ。